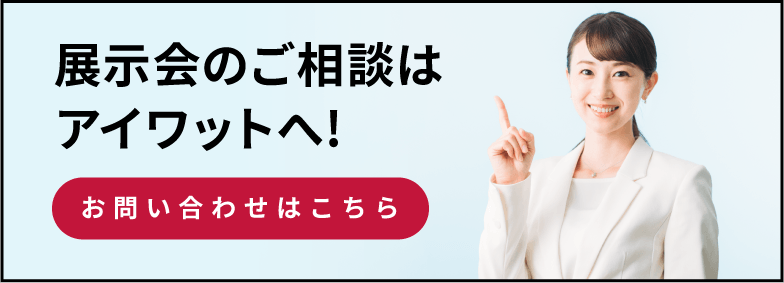出展も来場もこれで安心!
展示会で役立つ情報収集のコツ
2025/05/13

展示会は、来場者にとっては業界の最新動向や製品情報を効率よく集める場であり、出展企業にとってはターゲットニーズを把握し、競合との差別化を図る絶好のチャンスです。
しかし、ただ足を運ぶ、ただブースを出すだけでは、思うような成果が得られないこともあります。
本記事では、「出展者」と「来場者」の立場から、展示会で成果を上げるための「情報収集のコツ」を具体的に解説します。
しかし、ただ足を運ぶ、ただブースを出すだけでは、思うような成果が得られないこともあります。
本記事では、「出展者」と「来場者」の立場から、展示会で成果を上げるための「情報収集のコツ」を具体的に解説します。
目 次
2. 出展準備編|差がつく事前リサーチの進め方
(1) 来場者の属性を把握する
(2) 競合他社の展示内容をリサーチする
(3) 展示会テーマ・業界トレンドを押さえる
(4) 展示会視察は「初日+最終日」が効果的
1. はじめに

展示会は、企業と個人がリアルなコミュニケーションを通じて、有益な情報を収集・交換できる貴重な機会です。
来場者にとっては新たな技術や製品の発見、市場トレンドの把握ができる場であり、出展企業にとっては見込み顧客との接点や、リアルなニーズの把握につながります。 とはいえ、なんとなく参加するだけでは、時間と労力に見合った成果は得られません。限られた時間の中で「本当に必要な情報」を掴むためには、目的に合わせた事前準備と当日の動き、収集した情報の活用方法が重要です。
出展者と来場者、それぞれの立場から展示会を最大限活用するための情報収集術をご紹介していきます。
来場者にとっては新たな技術や製品の発見、市場トレンドの把握ができる場であり、出展企業にとっては見込み顧客との接点や、リアルなニーズの把握につながります。 とはいえ、なんとなく参加するだけでは、時間と労力に見合った成果は得られません。限られた時間の中で「本当に必要な情報」を掴むためには、目的に合わせた事前準備と当日の動き、収集した情報の活用方法が重要です。
出展者と来場者、それぞれの立場から展示会を最大限活用するための情報収集術をご紹介していきます。
2. 出展準備編|差がつく事前リサーチの進め方

(1) 来場者の属性を把握する
(2) 競合他社の展示内容をリサーチする
(3) 展示会テーマ・業界トレンドを押さえる
展示会には、その年ごとのテーマや業界での注目トピックが存在します。「市場の動向に合った展示内容」は来場者の注目度が格段に上がります。業界の最新ニュースや、主催者が発表している展示会のコンセプトを読み解いて、自社の展示にどう組み込むかを考えてみましょう。
(4) 展示会視察は「初日+最終日」が効果的
出展準備を進めるうえでは、実際に展示会を見に行くことも大切です。特に初日と最終日をチェックしておくと安心です。初日はブースの完成度や呼び込み方法など、出展者の「初動」が見られる貴重なタイミング。一方、最終日はコンセプトや接客品質がどれだけ維持されているか、運営体制の「持続力」を確認できます。
また、展示会によっては最終日の方が来場者数が多くなる傾向も見られます。視察の際には、時間帯や日程による人の流れの違いにも注目しておくと、実際に出展する際のスタッフ配置や呼び込みタイミングの検討に役立ちます。
また、展示会によっては最終日の方が来場者数が多くなる傾向も見られます。視察の際には、時間帯や日程による人の流れの違いにも注目しておくと、実際に出展する際のスタッフ配置や呼び込みタイミングの検討に役立ちます。
3. 展示会当日編|展示会本番での情報収集の工夫

展示会当日は、自社の魅力を伝える「営業活動の場」であると同時に、「マーケティングの場」でもあります。来場者との対話や行動から得られる情報は、展示会後の営業戦略に活かせる貴重な財産です。以下のような情報収集の工夫を取り入れてみましょう。
(1) アンケートでニーズを可視化
(2) 名刺交換+ヒアリングメモ
(3) 来場者の行動観察
どの資料がよく持ち帰られたか、どの展示に人が集まったかなど、来場者の行動観察も貴重なデータです。スタッフ間でこまめに状況を共有し、どの訴求が効果的だったかをリアルタイムで分析していきましょう。次回展示会や営業ツール改善のヒントになります。
(4) 「初日」を有効活用
出展企業が情報収集に力を入れるのにおすすめの日程は「初日」です。ビジネス目的で来場するバイヤーや決裁者、メディア関係者などキーパーソンが集まりやすく、そうした来場者から得られる反応や質問、関心のある製品・サービスの傾向は、今後の営業やプロモーションの方向性を見極めるうえで非常に参考になります。
4. 来場者編|展示会で効率よく情報を集めるには

(1) 目的を明確にする
(2) 事前に情報を収集しておく
(3) 質問リストを用意する
展示会では、短い時間で的確に情報を得る必要があります。そのためには事前に質問リストを作っておくのが効果的です。製品のスペック、価格帯、導入事例など、特に気になるポイントは項目別に整理しておきましょう。営業担当者との会話もスムーズになり、商談のきっかけにもなります。
(4) 早めに足を運ぶ
展示会を効率よく回るには、初日もしくは 2日目に行くのがおすすめです。ブースによっては最終日にはパンフレットやノベルティが在庫切れになっていることもあるため、早めに訪れることで、必要な情報を確実に手に入れることができます。また、午後は混雑しやすいため、比較的空いている午前中の方が落ち着いて回ることができます。
5. まとめ|情報収集を成功させる5つのポイント

出展企業は「来場者・競合・業界トレンド」を事前に把握し、戦略的にブース設計
当日は「アンケート・会話・観察」で、営業に活かせるリアルな声を収集
得られた情報はチームで共有し分析することで、今後の施策に再活用
展示会を単なるイベントで終わらせず、継続的なマーケティング活動に結びつける
来場者は「目的・質問・記録」を事前に整理して、有意義な情報収集の場に
展示会は一過性のイベントではなく、“情報”という武器を活かしてビジネスを前に進める場です。来場者・出展者それぞれの立場で正しい情報収集術を実践することで、その効果は何倍にも広がります。ぜひ次回の展示会では、この記事を参考に「情報を集め、活かす」視点を取り入れてみてください。